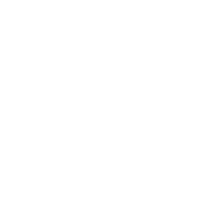大学院で生産性を維持する5つの工夫
Sophia Leung著(カナダMcGill大学、博士)

学術誌への論文掲載は遅れがちになるということを、博士課程を卒業したばかりの私は身をもって経験しています。
研究者としての生産性は一見すると発表した論文数だけで評価されるように思われますが、実際は論文を量産する以外にも、大学院で成果を上げ、高い生産性を示したことを証明できる様々な方法があります。そこで、論文掲載に苦戦している時は、CV(Curriculum Vitae)を充実させるとともにサイエンスコミュニティに貢献するための5つの少し型破りな方法を検討してみましょう。
1. ジャーナルクラブ(Journal Club)に投稿する
論文を読んだ時間を無駄にしないためにも、その内容に関するレビュー記事を執筆してみましょう。一部の学術誌は、博士課程の学生やポスドク研究員が最新論文の結果や意義をレビューしたジャーナルクラブ向けの記事の投稿を受け付けています。レビュー記事を執筆することで、その研究論文を若手研究者や異なる分野の研究者が容易に把握し、発見の真価を正しく認識してもらうことに貢献できます。それと同時に、自分自身のサイエンスコミュニケーションや批判的思考のスキルも身につけることができます。さらに魅力的なのは、レビュー記事が掲載されることで、研究者としての能力を示した実績が得られるという点です。
補足:概して、自身の研究について時間を割いて執筆されたレビュー記事は、研究者から歓迎されます。テーマにする研究論文の著者が共同研究をしたい相手であったり、つながりを持ちたい相手であったりした場合は、執筆後に自己紹介のメールを送ってみましょう。
レビュー記事を受け付けているジャーナルをいくつかご紹介します。
- The Journal of Neuroscience(https://www.jneurosci.org/content/jneurosci-journal-club)
- PNAS(https://www.pnas.org/journal-club)
2. PIと共に論文を査読する
実際に自分で研究を計画して実験するようになると、結果の解釈を左右する些細な事柄にも気付くことができる洞察力が養われます。このスキルは査読をするうえで非常に有益です。Nature誌のような学術誌は論文査読の過程に若手研究者が関わることを奨励しています。こうしたケースの場合、博士課程の学生を指導するPI(Principal Investigator)が学生に打診して共同で査読を行います(詳細はNature誌の取り組みをご覧ください:https://www.nature.com/nrm/for-referees/reviewer-initiatives#ECR)。学術誌によっては、このような学生による査読の貢献を公表するところもあります。査読には匿名性が求められる場合があるため、学生の貢献がクレジットされないとしても、今後PIを目指す学生やサイエンスコミュニケーションに携わりたいと希望する学生にとっては良い訓練になるはずです。そのため、PIには論文査読を手伝うことに興味があるということを必ず伝えておきましょう。
3. 非営利団体のために執筆する
もし疾病に関する研究に携わっている場合は、研究論文を患者やその家族、一般の人々向けにわかりやすく翻訳・解説するライターを募集している団体・組織やウェブサイトに注目しましょう。例えば、National Ataxia FoundationによるSCASourceは、脊髄小脳失調症(SCA:Spinocerebellar Ataxias)研究に携わるボランティアの研究者によって平易な言葉で書かれた記事を公開して、研究者と患者の間の情報交換を促進し、患者が最新の科学的進展を知ることができるように活動を展開しています。研究分野に関する専門知識をコミュニティに還元すると同時に、コミュニティに関心を持ち重視しているかを行動で示すことは、一般的に、助成金や奨学金等の資金援助における「社会参加(Social involvement)」の要件を満たす行為となります(参考例:BrainPost(https://www.brainpost.co/)等の学生が参加できるコミュニティが存在します)。
4. 研究仲間と協力しあう
他の研究者に専門知識を提供し、論文に名前を掲載してもらいましょう。所属研究室でただ1人ウェスタンブロットの実験手技を知っている、あるいはPythonによるプログラミングができるといった場合、メンバーにその方法を伝授するかわりに、相手のプロジェクトに参加して執筆協力者・共著者(Contributing author)として論文に名前を載せてもらえないか申し込んでみましょう。逆に、他の研究者のスキルを拝借して自身のプロジェクトの進行を助けてもらうこともできます。科学研究は、共同で進めると最良の成果が得られます。なぜなら、議論を重ねることで異なる見解が融合し、新たなアイデアが創出されるからです。その他にも、共通認識を築きあげ、フィードバックを受け入れることに慣れる—言い換えればCVに「他の研究者とチームを組んで共同研究をした実績あり」と書き込むことのできる—良い訓練になります。そのため、今後他の学生の研究発表に参加する際は、共同研究のチャンスに注目してみましょう。
5. 進捗の速そうなプロジェクトを担当する
ある同僚は、インパクトは大きいものの、結果が出るのに何年も要すると予想されるプロジェクトを指揮していました。彼女が実験条件の最適化に関する「Method paper」を執筆したのは賢明な判断でした。Method paperは奨学金申請にあたって進捗を示すのに非常に役立ち、将来的に発表する論文への信頼を確立するのに一役買いました。同じような状況になった場合は、例えば、特性解析に関する論文や過去に院生が手掛けていた研究といった、比較的早く結果が出ると予測されるプロジェクトがあるか調べてみましょう。それに加え、原稿の執筆は間違いなく有益な経験となります。
特に、費やした努力とその結果が比例しない時のように、学位を取得するまでの間に歯がゆさを感じる出来事は多々存在します(大学院とはそういうものです)。とはいえ、良質な結果を得るための作業には時間がかかり、優れた研究成果を出すにはもっと時間を要するということを心に留めておきましょう。論文が学術誌に掲載されるまで5年以上かかることも珍しくありません。地道に実験に取り組むと同時に、上述したアイデアを常に念頭におきながら、生産性を維持して質の高い研究を心がけましょう。